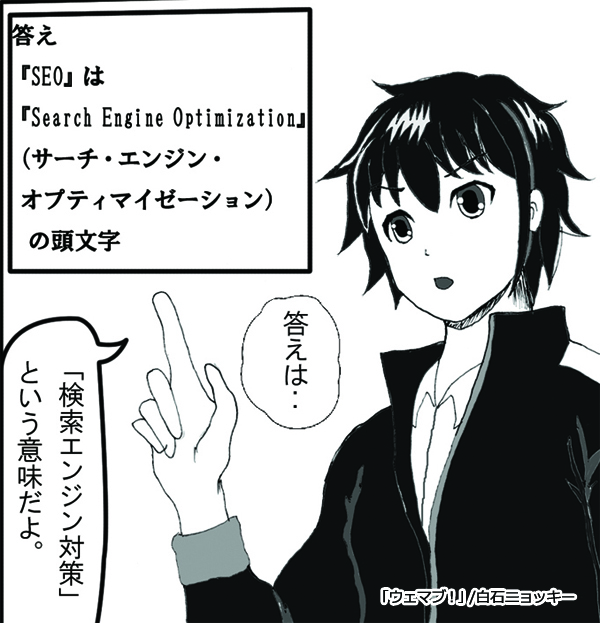
【SEO】リンクビルディング(被リンク獲得)のポイントまとめ
リンクビルディング(被リンク獲得)についてすべきことのまとめです。
今やっておくべき「リンクビルディング見直し大作戦」
1. そのリンクの価値を判断する
2. ローカルリスティング
これは今でも非常に有効だ。ローカルビジネスへのサイテーション(引用、言及)はさまざまなプラットフォーム上にあり、Moz LocalやYextなどのサービスを利用すれば、少しでも早く仕事にとりかかれる。
こういったサービスの多くは、対象のビジネスが記載の場所に実在することをグーグルに伝えるものだ。一貫性のあるビジネス情報(会社名、住所、電話番号などのあらゆる情報)を提供する。ただし、実際にはあまり話題になっていないことだが、これらのローカルリスティングの一部はまったくグーグルにインデックス登録されていない。考えてみると、Yellowpages.comのサイトはおそらく、1日に数千件もの新しいリスティングを追加している。グーグルが、それらすべてをインデックス登録したいと思うだろうか?
したがって、ビジネスリスティングを登録する場合、ローカルSEO担当者が昔からやっているのは、サイト上にページを作成して、ネット上での居場所を記載することだ。
これらのローカルリスティングへのリンクはグーグルがインデックス登録するのに役立つし、サイトにブーメラン効果のようなものをもたらす。この施策は今でも有効で、みなさんの役に立つことを願っている。
3. リンクされていないブランドメンションを把握する
リンクを獲得できる最も簡単な方法の1つは、自分のブランドや会社に言及しているが、リンクしていない人を把握することだ。たとえば、ある記事ではSEO企業の素晴らしさについて書いていて、Mozに言及しているが、Mozにリンクはしていない。
そういう場合は、「こんにちは、よろしければリンクを追加していただけませんか? ご協力いただけると本当に助かります」と連絡してみるだけでいい。
4. リンク切れを修正する
5. HARO(Help a Reporter Out)
■HARO(Help a Reporter Out)
6. とにかく素晴らしい存在になる。クールになる。素晴らしいコンテンツのスポンサーになる
7. 依頼またはアウトリーチする
8. COBC(Create Original Badass Content:オリジナルのすごいコンテンツを作成する)
多くの人がこのことについて話すのを耳にする。リンクビルディングについて言えば、「リンクビルディングは死んだ。ただ素晴らしいコンテンツを作成すれば、人々は自然にリンクしてくれる。最高だ」といった具合だ。
確かにそうなれば最高だが、リンクビルディングと適切に組み合わせることにも利点はあると思う。リンクビルディングという考え方があって、それからリンクアーニングという考え方がある。しかし、その2つが交わったところにこそ、最大限の効果が得られる絶好の領域があるのだ。
やってはいけないこと
1. 特定のアンカーテキストを使うよう依頼しない
故エリック・ワード氏はこのことに言及していたが、決してアンカーテキストを求めない姿勢を熱心に支持していた。同氏は、ウェブサイトは適切と思われる方法で自由にリンクされるべきだと言っていた。その方が自然に見えるだろう。
グーグルはこの方がオーガニックだと考えるだろうし、長期的にはサイトのためになる。したがって、これはどちらかというと提案だ。これ以外の項目は、間違っても絶対にしてはならないことだ。
2. PageRankを引き渡すリンクを売買してはならない
ただし、nofollowタグ付きのリンクは売買してもかまわない。そうしたリンクは、それが有料であることを明記しているのであり、広告であろうと信頼できないコンテンツであろうと関係ない。そのため、必ずよく調べて効果を理解する必要がある。
3. 隠しリンク
4. 低品質のディレクトリリンク
5. サイト全体のリンクも、かなりスパムっぽく見える
フッターリンクであろうとトップレベルのナビゲーションリンクであろうと、サイト全体にリンクを張るのは絶対にやめるべきだ。スパムにしか見えなくなる。これは避けよう。
6. 過剰に最適化したアンカーリンクテキストを含むコメントリンク
これは特に避けたい。これも他の項目とまったく同じだ。スパムのように見える。長い目で見て役に立たない。繰り返しになるが、そもそもこのようなリンクにどんな価値があるというのか? 使うのはやめよう。
7. ゲスト投稿の乱用
8. 自動化されたツール
9. リンクスキーム(プライベートリンクネットワーク、プライベートブログネットワーク)
10. リンク交換
SEOコンサルタントの感想
●ローカルSEO担当者が昔からやっているのは、サイト上にページを作成して、ネット上での居場所を記載すること
▼これは「サイトを作れ」という意味かな?それともサイテーションの為に「運営者情報」も表記すべき、という事も含んでいるのか?
そうでないとしても「運営者情報」は書いた方が良いですね。
●「こんにちは、よろしければリンクを追加していただけませんか? ご協力いただけると本当に助かります」と連絡してみるだけでいい。
▼ものすごい昔の被リンク獲得方法で、私も2010年の著書に書きましたね。
でもお金かからないですしだめもとでやるのは良いですね。
●とにかく素晴らしい存在になる。クールになる。素晴らしいコンテンツのスポンサーになる
●オリジナルのすごいコンテンツを作成する
▼言われるまでもないですが、あえて書いたのでしょう。
●決してアンカーテキストを求めない姿勢
▼SEOをかじっていると「できればテキストリンクで…」と言ってしまいますが、なるべくお任せする方法で、
リンクして頂けると言うだけでありがたい、という姿勢ですね。
●ただし、nofollowタグ付きのリンクは売買してもかまわない
▼「SEO目的」ではなく「広告、集客目的のリンク」ならOK。
●フッターリンクであろうとトップレベルのナビゲーションリンクであろうと、サイト全体にリンクを張るのは絶対にやめるべきだ。スパムにしか見えなくなる。これは避けよう。
▼これはなかなか厳しいですね。。
●私がみんなに聞きたい疑問の1つは、リンクを否認するか、それとも否認しないかだ。
これについては、どちらとも決着がつかない議論を耳にしてきた。否認ファイルは今も有効なのだろうか? それとも効果はないのか?
▼リンクの否認は気になるならしておくのが良いですね。
▼「サイテーション(引用、言及)」については最近よく見る話題ですね。
どんどん重要性を増しているように思えます。
[被リンク記事]



